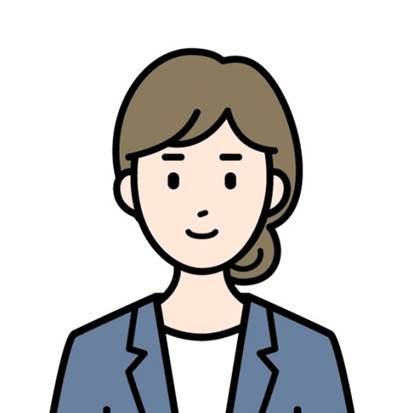社会人向け公務員試験で実施される論文・作文試験は、配点のウエイトがあまり大きくないため、対策も後回しにされがちです。
しかし、その点数のわずかな差が合否を決めたりすることもよくあることで、やはりおろそかにはできません。
このブログでは、公務員試験の論文試験・作文試験に臨む際の対策方法について、具体的なステップと助けになるヒントを解説します。
本ページはプロモーションが含まれています
【社会人採用】公務員試験の論文試験・作文試験対策の進め方
論文試験・作文試験の基本ルール

論文試験と作文試験のちがい
公務員試験の文章作成系の試験には、「論文試験」と「作文試験」の2つがあります。
まず、論文試験と作文試験を定義すると、次のとおりです。
根拠や客観的な事実などを基にして課題の答えを書くもの。
公務員の職務に関連する問題や社会的な課題について、応募者自身の視点や専門知識を駆使して論じる必要があります。
【特徴】
・専門性が求められる: 論文試験は、応募者の専門分野に関連する問題を扱うことが多いため、深い知識と専門性が求められます。
・論理的な論述が必要: 論文は一貫性があり、論理的に展開された議論を含む必要があります。主張や意見を裏付けるために具体的な根拠や事例を示すことが重要です。
・調査研究やデータの活用: 論文試験では、信頼性のある情報源から得たデータや統計を利用して、主張を裏付けることが求められることがあります。
自分の体験や感想を書くのもの。
論文試験とは異なり、特定の専門分野に関する知識は問われず、一般的なテーマに対して応募者の表現力などを測ることが主な目的です。
【特徴】
・一般的なテーマ: 作文試験のテーマは一般的なものが多く、日常生活や社会に関する問題などが出題されることが一般的です。
・個人の表現力を重視: 作文試験では、応募者の個性や表現力を重視します。自己の経験や視点を示し、感情や思考を的確に伝えることが重要です。
・論理性よりも文章のクオリティ: 論文試験ほど厳密な論理性が求められるわけではなく、文章のクオリティや読みやすさが重視されます。
論作文試験の評価基準
論文試験・作文試験では、どのような点を評価されるのか。
評価は、形式面の要素と内容面の要素で構成されます。
まず、論文試験・作文試験に共通する形式面の要素として、次の点が考えられます。
【形式面の評価要素】
・論理展開が優れているか。
・文章構成が適切か。
・誤字脱字がないか。(多くないか)
・分量が十分であるか。
加えて、内容面の要素が評価されます。
【内容面の評価要素】
・テーマに適切に対応しているか。
論作文試験共通の対策(形式対策)

まずは形式対策
論文試験・作文試験とも、まず、最低限の形式対策の必要があります。
1.論理展開が優れているか
論文試験や作文試験では、論理的な展開が求められます。
文章全体が一貫性を持ち、段落間のつながりが明確であることが重要です。
対策としては、以下の点に注意しましょう。
・アウトラインをしっかりと作成し、メインポイントやサポート情報を整理する。
・段落ごとに主題文やトピック文を使って段階的な論理を構築する。
・論理的なつながりを示す接続詞などを適切に活用する。
2.文章構成が適切か
適切な文章構成は、読み手がスムーズに理解できる重要な要素です。
対策としては、以下の点に注意しましょう。
・イントロダクションでテーマや目的を明確に提示する。
・メインポイントを順序立てて展開し、論点を明確にする。
・まとめをしっかりと行い、結論を示す。
3.誤字脱字がないか(多くないか)
誤字脱字が多い文章は信頼性を損ないますし、読み手に不快感を与える可能性があります。
対策としては、以下の点に注意しましょう。
・十分な時間をかけて文章を校正し、誤字脱字をチェックする。
・文章を何度も読み返すことで見落としを防ぐ。
4.分量が十分であるか
論文試験や作文試験では、指定された分量を満たすことが求められます。
対策としては、以下の点に注意しましょう。
・アウトラインを作成し、それぞれのセクションの分量を見積もる。
・具体的な事例や説明を追加することで、文章を充実させる。
・タイムマネジメントを意識し、時間内に分量を達成できるよう努力する。
具体的な対策は、市販の公務員試験用の対策本で十分対応できます。
(次の参考書も参考になります。)
論文試験対策(内容対策)

内容対策は重要
さきほどの形式対策は対策本を読めば、多くの受験者が同じようなレベルに到達します。
このため、他の受験者との差別化を図るためには、内容対策こそ重要となります。
論文試験の内容で差別化を図る場合には、独自に、受験する団体などの課題をしっかりと把握し、自分の考えをまとめる作業が必要です。

このブログでおすすめする論文試験の内容対策は、
「現在直面している行政課題に対して、幅広く、自分の考えをしっかりと一度整理しておくこと」です。
ポイントは、
・行政課題を幅広く把握しておく
・「自分の考え」を整理する
というところです。
この作業をおすすめする理由は、2つあります。
理由1:どんなテーマにもある程度対応できるようになる
理由の1つめは、幅広い課題に一つ一つ準備をしておけば、論文試験のどんなテーマが来ても、ほぼ対応できるようになることです。
論文試験で一番怖いのは筆が止まる(全く書けない)ことです。
これを防ぐことができれば、精神的な安心感につながります。
論文試験のテーマは、大抵、その団体が抱えている課題に関する内容が採用されることが多いです。
仮に、そうでなくても、行政が抱える「社会課題」は全国的に大きくは変わりませんので、事前に整理したものに何らかのつながりはあります。
それらをうまく繋げて、準備した内容を使って書くことができるため、試験課題に対して筆が止まるということは起こりません。
オススメ理由2:面接試験対策にもなり、入庁後にも役立つ
2つめは、この過程で得た知識を面接対策にも使えるということです。
面接で団体の課題など難しい質問や集団討論などがあっても、論文対策で得た知識や考察したものがあれば、自信を持って対応できます。
以上の理由から、論文試験の内容対策のメリットは大きいと考えます。
面倒な作業と思わず、ぜひ地道に取り組んでいただきたいと思います。
急がば回れ、というわけね。早いうちから、また、教養試験対策の合間合間に、少しずつやっておくことにするわ。
きっとライバルとの大きな差になるはずです。
論文の展開の仕方
論文は論理的な構成と展開が重要であり、読み手に明確なメッセージを伝えるために適切な展開が必要です。
論文の展開方法を理解し、効果的に使用することで、文章の説得力や読みやすさを高めることができます。
様々な展開方法はありますが、ここでは一例をお示しします。
1.イントロダクション(導入)
論文の展開はイントロダクションから始まります。
イントロダクションは読み手に対して論文のテーマや目的を明確に伝える部分です。興味を引く引用や舞台設定、問題提起、背景情報などを使って、読者の関心を惹きつけることが大切です。
また、本文の主張や構成を示すことで、論文の方向性を示すことが重要です。
2.メインポイントの提示【課題の提示】
論文の展開では、イントロダクションで示した主題に対してメインポイントを提示します。
3.サポート情報の提供【原因分析】
メインポイントをより具体的に説明するために、サポート情報を用いることが効果的です。
サポート情報は具体的な事例、統計データ、専門家の意見、歴史的な背景などを含みます。
4.論理的な結びつけ【解決策の提示】
論文の展開では、メインポイントを論理的に結びつけることが重要です。
前後の段落との論理的なつながりを示すことで、文章全体の一貫性が保たれます。
接続詞などでスムーズな移行を行いましょう。
5.コンクルージョン(結論)
論文の展開はコンクルージョンで結びます。
コンクルージョンでは、論文全体のまとめと結論を示します。
イントロダクションで示したテーマや目的に対して、本文の内容との一致や洞察を示すことが重要です。
論文の展開は読み手に対して論理的で理解しやすい構造を持つことが不可欠です。
以上のポイントを押さえながら、テーマを明確にし、段階的に展開していくことで、説得力のある論文を書くことができるでしょう。
また、論文を読み返し、改善することで展開の質を高めることも重要です。
ところで、こうした論文を、何のツールも頼りにできない中、短時間で書くためには、どうしたらよいでしょうか。
その場でゼロから構築するのは、いくら新聞を毎日読んでいて自信のある人でも難しいと思います。
何がそのテーマの課題なのかもそうですし、分析するためのデータ的なものも、試験会場で考えて浮かんでくるものではありません。
つまり、あらかじめ準備しておくことが必要となります。
論文対策では、団体の総合計画などを活用した対策がおすすめです。
具体的な方法は、次の記事へと進んでください。
⇒論文試験対策はこちら
【参考】生成AIを活用した論文案作成
生成AIを活用し、次のようなプロンプト(指示文)を入力すれば、論文案の参考程度には使えます。(ただし、手直しはかなり必要ですので、あくまで参考程度です。)
【プロンプト(指示文)の例】
次の内容で論文を書いてください。
なお、これは公務員試験に合格するために作成する論文です。
<論文テーマ>
「行政事務へのChatGPTの活用について」
<文字数>
1000文字程度
<構成>
1.イントロダクション(導入)
2.メインポイントの提示【課題の提示】
3.サポート情報の提供【原因分析】
4.論理的な結びつけ【解決策の提示】
5.コンクルージョン(結論)
<文章に盛り込むキーワード>
・個人情報漏洩の課題
・行政コスト削減への寄与


作文試験対策(内容対策)

作文試験対策は面接対策の延長のつもりで
論文試験が「根拠や客観的な事実などを基にして課題の答えを書くもの」に対し、
作文試験は「自分の体験や感想を書くのもの」です。
ただし、作文試験は何でも書いていいというわけではなく、「体験と感想」は、面接試験対策の「行動事例」と「志望動機」の要素が必要となります。
作文試験の準備1(体験談の整理)
体験談については面接試験の「コンピテンシー面接」の考え方と同じです。
入庁後に求められる「コンピテンシー」を把握して、それを意識した体験談を選んで書くことが重要です。
「コンピテンシー面接」については、次の記事に書いていますので参考にしていただき、求められる要素ごとの体験談を整理しておきましょう。
作文試験の準備2(「考え」の整理)
もう一つの「考え」ですが、「決意」や「志」につながる設問が多いと思います。
これは面接試験の「志望動機」と重なりますので、自分が公務員になぜなりたいのか、何をしたいのかということをじっくりと時間をかけて考え、整理しておきましょう。
まとめ
論文試験と作文試験は、試験の目的や求められるスキルに違いがあるため、対策を立てる際にはその点を把握しておくことが大切です。
論文試験では専門的な知識と論理的思考が求められる一方、作文試験では自己表現と文章のクオリティが重視されます。
しっかりと違いを理解し、それぞれの試験に適したアプローチを取り入れることで、より効果的な対策を行ってください。