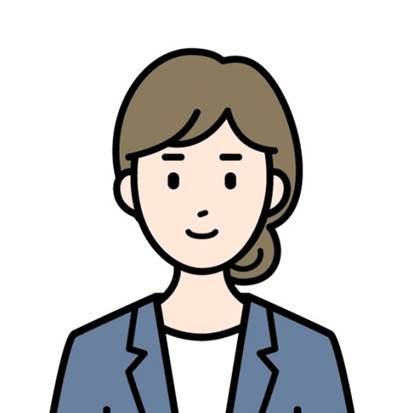社会人向け公務員試験に関するよくある疑問まとめ

社会人経験者・就職氷河期世代の公務員試験に関するよくある疑問について、
FAQ形式で整理していきます。
本ページはプロモーションが含まれています
試験制度について

●社会人の公務員試験の1年間のスケジュールは?
試験スケジュールは、まず、試験実施団体による翌年度の「試験実施計画」の公表から始まります。
試験実施団体ごとに、おおむね3月頃までに、ホームページで、翌年度の試験日程・内容についての概要が示されますので、受験を考えている団体のホームページは必ずチェックしましょう。
社会人経験者・就職氷河期世代の試験は、春シーズンと秋シーズンに大別されます。
受験を考えている団体に応じて対策の開始時期も考える必要があるでしょう。
●試験日程、受験資格、試験内容などの試験概要はどこを確認したらいい?
受験を考えている先のホームページに、試験実施計画がまず掲載され、詳細は受験案内で示されます。
国家公務員であれば人事院、都道府県庁であれば各都道府県の人事委員会のホームページで公表されます。
このブログでも、順次整理していきます。
(関連記事)公務員試験応援ブログトップページ
●試験の難易度は上級(大卒程度)?初級(高卒程度)?
おおむね、
・社会人経験者試験 ⇒『社会人基礎試験』または『教養試験(上級)』が多い
・就職氷河期対象試験 ⇒『教養試験(初級)』が多い
ですが、必ずしもそうではない場合もあります。
過去の傾向を参考にしながら、最終的には、受験を考えている団体のホームページに掲載される試験実施計画、受験案内などの情報で、必ず試験内容をチェックしてください。
(なお、試験実施計画は、年明けから春にかけて策定され、国家公務員であれば人事院、都道府県庁であれば各都道府県の人事委員会のホームページで公表されます。)
試験対策の軸は通信講座で進め、試験の難易度の差異をそれぞれに応じた問題集で補完することをおすすめします。
(関連記事)社会人向け公務員試験の対策にオススメの問題集
●働きながら受験してもいいの?
働きながら受験することはできます。
仕事を辞めてから受験する必要はありません。
面接で、採用できる確率を確認するために、「会社には話しているか?」、「円満に退職できそうか?」ということは聞かれると思いますが、それで合否に影響はありません。
●地方公務員の場合、出身地などでなくても受験できる?
受験資格で住所要件がある場合を除いて、出身地は関係ありません。
ただし、面接官側は、自分や配偶者の出身地でもなく、これまで全く縁のないのに受験してきた場合は「練習受験なのではないか?合格しても来ないのではないか?」ということが気になります。
確認のために、面接では、受験理由を聞かれると思いますので、その想定はしておきましょう。
●年齢が高いと合格しにくいの?
受験資格の上限年齢に満たしていれば、受験をすることができるため、年齢だけをもって合格を判断することはありません。
一方で、試験実施側の求めている人材像との兼ね合いなどから、面接試験の評価の中で加味される要素には少なからず影響するため、結果として、完全にフラットな扱いにはならないのは、やむをえないところです。
ただし、50代でも合格者は出ていますので、十分にチャンスはあります。
●学歴や経歴で合格が決められたりするの?
厚生労働省の「公正な採用選考」では、表面上の学歴や経歴のみで合否にバイアスをかけないようにすべき、という趣旨のことが指導されており、採用する側はそれを守る必要があります。
面接では、表面上の内容ではなく、人物の中身を見る質問をし、評価視点もそれに基づいて行われます。
●本命の受験先以外を併願してもいいの?
日程さえ一緒でなければ、いくつか受験することができます。
事情があって、地元に帰って転職しないといけない理由などあれば、県庁と市役所を受けるなど、ぜひ併願すべきです。
ただし、最初から辞退予定で練習受験として併願することは、私はおすすめしません。
●過去に不合格になった団体を再度受けていいの?
基本的に、受験資格で特に制限をかけるようになっていない限り、何度も受験することは可能です。
しかし、受験が可能ということと、合格の可能性があることは話が違います。
面接まで進んでいない場合は積極的に挑戦すべきですが、過去の試験で面接まで進んだ場合は、結果によって対応が変わってきます。
(関連記事)社会人向け公務員試験の再チャレンジに必要な対策
●都道府県庁ってどんな仕事をしているの?
都道府県庁の仕事は、国の省庁や市役所に比べてわかりにくい面があります。
以前は国と市町村をつなぐ役割で、市町村を指導する立場でしたが、今は、いずれも対等ですので、基本的には、都道府県内の市町村のコーディネート役と考えるとよいと思います。
(関連記事)都道府県庁の職員構成、仕事と組織ってどうなっているの?
(就職氷河期世代対象試験)
●国家公務員の就職氷河期世代対象試験は1次試験を通過するのが難しすぎるのでは?
初年度の2020年度の倍率、正答ラインはさすがにシビアなところがあり、1次試験を通過することが至難の業という印象がありました。
2022年度は2021年度と比べてやや持ち直したものの、初年度の正答ラインと比べれば低下しており、対策さえしっかり行えば、十分に通過できるレベルになっていると言えるでしょう。
(関連記事)
【傾向と対策!】国家公務員試験(就職氷河期世代)3か年の試験状況分析
試験対策について

●どのくらい勉強したらいいの?
試験の難易度にもよるため一概には言えません。
早ければ早いにこしたことはない、というありきたりな回答になりますが、大事なのは、教養試験対策ばかりに集中しすぎて、論作文や面接の準備がおろそかにならないように気をつけることです。
なお、実務教育出版の「早わかりガイドブック」の中には、合格者の学習時間のデータが少し載っているので、気になる方は、参考になるかもしれません。
(関連記事)公務員への転職をめざす人の入門書「早わかりブック」とは?
●教養試験対策はどうしたらいい?
教養試験対策ばかりに時間を取られていてはいけませんが、突破しなければそこで終わりでもあり、そのバランスが重要です。
まずは、しっかり「理解」をすることが必要ですが、忙しい社会人が「独学」で行うのは、なかなか無理があります。
そこで、理解の軸を通信講座で行うことをオススメしています。
●論文・作文試験対策はどうしたらいい?
論文試験は、形式よりも内容重視で進めてください。
内容に関しては、対策本や通信講座などを鵜呑みにするのではなく、自ら調べ、「自分の考え」を整理するところまでの作業過程が必要と考えます。
ここは他の受験者との「差別化」を図るポイントです。
一方、作文試験は「自分の体験や感想を書くのもの」のため、事前の準備は複雑ではありません。
ただし、自分の体験を何でも書けばいいというわけではなく、面接試験の「コンピテンシー面接」の考え方と同じで、入庁後に求められる「コンピテンシー」を把握して、それを意識した体験談を選んで書くことが重要です。
また、自分が公務員になぜなりたいのか、何をしたいのかということをじっくりと時間をかけて考え、整理しておきましょう。
●面接試験対策はどうしたらいい?
面接試験は、試験全体で最も重要視される試験です。
特に「使命感」の要素が最も重要であるため、これにつながる「志望動機を追求・整理」することに、しっかりと時間を使いましょう。
また、他の受験者と「差別化」を図るのであれば、他の受験者が取り組まない要素で差をつけることが重要です。
公務員試験の勉強と並行して進めることはなかなか難しいと思いますが、情報系資格の取得や勉強をしておけば、面接でアピールでき、大きなポイントとなります。
特に「情報スキル」について学んでおくことをオススメしています。
中でもAIは今後の行政で間違いなく重宝される知識で、面接官もほぼ知らない分野なので、非常に強力な加点要素となるでしょう。
●択一問題なら、勉強しなくても合格できることもある?
全くのヤマ勘では、確率的に合格はほぼ絶望的です。
過去に勉強していた記憶もほとんど当てになりませんので、ある程度の対策は必要です。
(関連記事)公務員試験(教養試験)をノー勉で突破できるか確率を出してみた
●受験で気をつけることは?
公務員試験の日程は、梅雨や台風シーズンに実施されることが多く、交通遅延リスクを考慮する必要があります。
社会人を対象とした試験では、そうした危機管理も含めて求められますので、悔いが残らないよう試験会場近くに前泊するなどの対策をおすすめします。
(関連記事)公務員試験の前日は会場の近くに宿泊した方がいい理由